冬に白内障が悪化するって本当?寒さと乾燥が目に与える影響を眼科医が解説
- 2025年11月19日
- 白内障
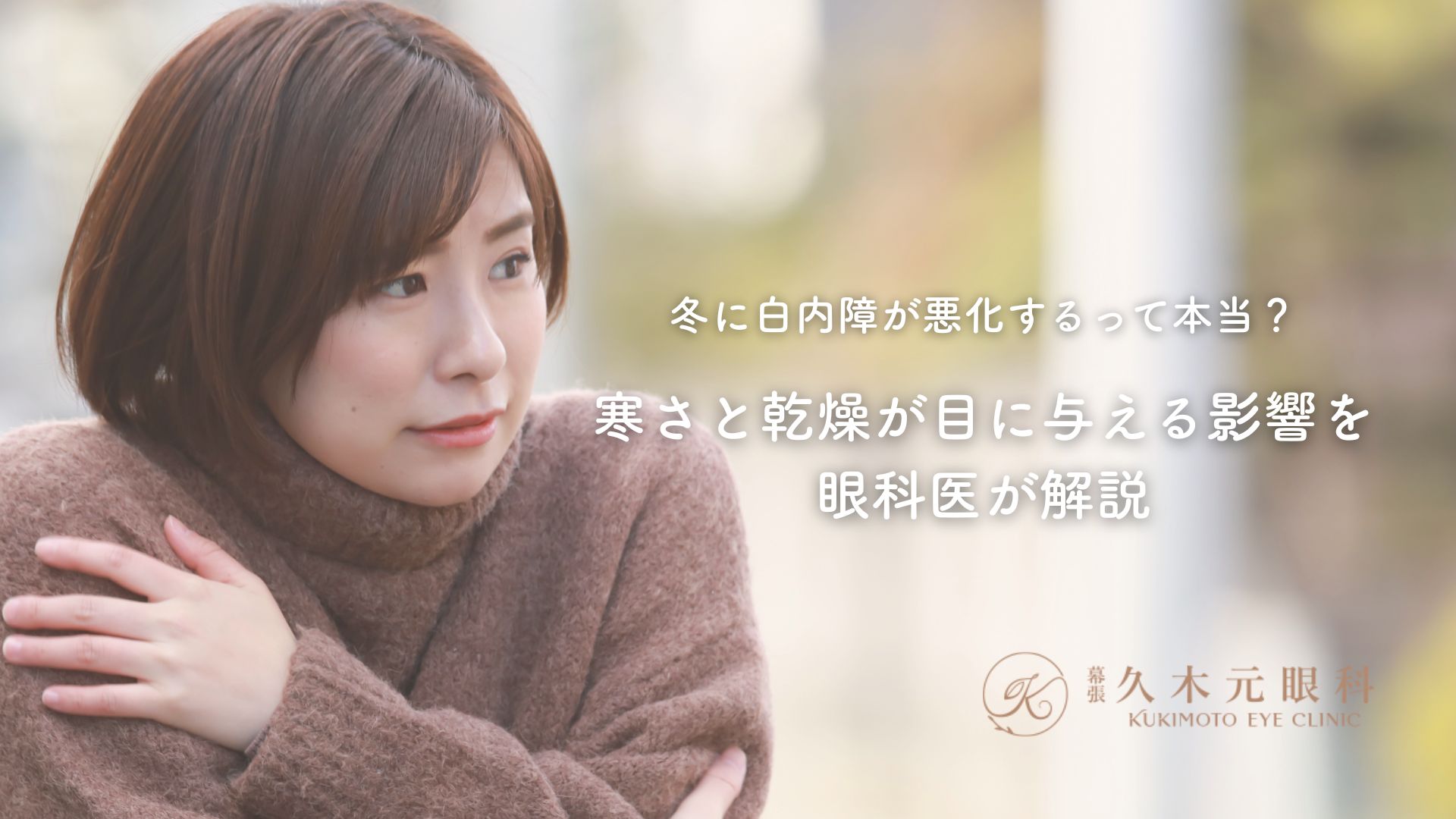
「冬になると目がかすむ気がする」「白内障が悪化しているのでは?」と不安に感じている方はいませんか?
寒さが厳しくなる冬の季節は、私たちの目にとって過酷な環境です。乾燥した空気、暖房による室内の湿度低下、冷たい風・・・これらの要因が目に様々な影響を与えます。
白内障と診断されている方にとって、冬の環境変化は特に気になるポイントでしょう。実際のところ、冬に白内障が悪化するのでしょうか?
この記事では、東京医科歯科大学病院で白内障・屈折矯正外来の主任を務めた経験を持つ眼科専門医として、冬の環境が目に与える影響について詳しく解説します。
冬の環境が目に与える影響とは
冬は一年で最も目にとって厳しい季節の一つです。
外気温の低下、湿度の急激な減少、そして室内では暖房器具がフル稼働・・・このような環境の変化が、目の健康に大きな負担をかけています。特に、乾燥した空気は涙の蒸発を促進し、目の表面を守る涙液層のバランスを崩してしまいます。
乾燥が引き起こす目のトラブル
冬の乾燥は、目にとって深刻な問題です。
湿度が低下すると、涙の蒸発速度が上がり、目の表面が潤いを失いやすくなります。その結果、ゴロゴロとした異物感、充血、かゆみといった不快な症状が現れます。さらに、エアコンやストーブなどの暖房器具を使用することで、室内の空気がさらに乾燥し、症状が悪化する傾向にあります。
特に注意が必要なのは「ドライアイ」です。
ドライアイは、涙液層の安定性が低下する疾患で、目の不快感や視機能異常を引き起こします。
気温の変化と血管への影響
冬の寒さは、血管にも大きな負担をかけます。
急激な温度差は血管を収縮させ、血流を悪化させます。これは目の奥にある網膜の血管にも影響を及ぼし、場合によっては「動脈閉塞」や「静脈閉塞」といった深刻な状態を引き起こすことがあります。これらの症状は急激な視力低下を招くため、早期の治療が非常に重要です。
また、気温の低下により眼圧が上昇することもあります。
眼圧の上昇は、緑内障のリスクを高める要因となります。緑内障は自覚症状がほとんどないため、40歳を過ぎたら定期的な眼科検診が必要です。
白内障は冬に悪化するのか?
結論から申し上げますと、白内障そのものが冬に急激に進行するわけではありません。
白内障は、目の中の水晶体が年齢や紫外線、病気などの影響で徐々に濁っていく疾患です。この濁りは、季節によって突然悪化するものではなく、長い時間をかけてゆっくりと進行していきます。
冬に「見えにくさ」を感じる理由
では、なぜ冬に白内障が悪化したと感じる方がいるのでしょうか?
その主な理由は、白内障そのものの進行ではなく、冬特有の環境要因が重なることにあります。乾燥によるドライアイの悪化、涙の量や質の低下、そして暖房による目の疲労・・・これらの要因が複合的に作用し、視界のかすみや不快感を増幅させているのです。
白内障を既に患っている方は、元々視界がややかすんでいる状態です。そこにドライアイや目の乾燥が加わると、さらに見えにくさが強調されてしまいます。これが「冬に白内障が悪化した」と感じる大きな要因です。
紫外線と白内障の関係
意外に思われるかもしれませんが、冬でも紫外線対策は重要です。
冬は太陽の位置が低く、雪面からの反射もあるため、目に入る紫外線量が増加することがあります。特に、スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツを楽しむ方は注意が必要です。
長期的に見ると、紫外線の蓄積は白内障の進行を早める可能性があります。
外出時にはサングラスやメガネを着用し、冷たい風やほこり、紫外線から目を守ることをおすすめします。
冬に起こりやすい目のトラブル

冬は白内障以外にも、様々な目のトラブルが起こりやすい季節です。
ここでは、特に注意が必要な眼科疾患について詳しく解説します。
ドライアイの悪化
冬のドライアイは、多くの方が経験する症状です。
空気の乾燥、暖房の使用、そして長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用・・・これらの要因が重なることで、まばたきの回数が減少し、涙の蒸発が加速します。その結果、目がゴロゴロする、充血する、かゆみを感じるといった症状が現れます。
特に、画面に集中することでまばたきが少なくなると、ドライアイが悪化しやすくなります。
また、寒さで血流が悪くなり肩こりがひどくなることもあります。ドライアイは眼精疲労の原因となり、肩こりをさらに悪化させ、頭痛につながることもあるため注意が必要です。
結膜炎とアレルギー性疾患
冬は結膜炎にも注意が必要です。
結膜炎は、目の表面を覆う結膜に炎症が起こる病気で、乾燥やウイルス感染などにより発症します。目が充血し、かゆみや異物感を感じることがあります。また、風邪やインフルエンザが流行する冬は、ウイルスが目に感染し、充血や涙が止まらないといった症状を引き起こすこともあります。
さらに、空気が乾燥している時期の室内は、ハウスダストや動物の毛、花粉などのアレルゲンが浮遊しやすく、アレルギー性結膜炎の症状を誘発します。
血管閉塞のリスク
冬の寒さは、目の血管にも影響を与えます。
気温の大きな変化は血管に負担をかけ、脳卒中や心筋梗塞などのリスクを高めますが、同様に目の奥にある網膜の血管にも影響します。網膜動脈閉塞や網膜静脈閉塞が起こると、急激な視力低下を引き起こします。動脈閉塞の場合は治療が非常に難しく、静脈閉塞の場合でもレーザー治療などの早期対応が必要です。
また、結膜下出血も冬に起こりやすい症状の一つです。
結膜の血管が切れ、白目が真っ赤になりますが、自覚症状はほとんどなく、視力に影響はありません。出血は2週間程度で自然に吸収されます。
冬の目を守るための対策
冬の厳しい環境から目を守るためには、日常生活での工夫が大切です。
ここでは、具体的な対策方法をご紹介します。
室内環境の整備
室内の湿度を適切に保つことが、目の乾燥を防ぐ最も効果的な方法です。
加湿器を使用し、湿度を50~60%程度に保つようにしましょう。加湿器がない場合は、濡れタオルや洗濯物を部屋に干す、観葉植物を置くといった方法も有効です。ただし、加湿器を使用する場合は、定期的に掃除をして清潔な状態を保つことが重要です。汚れた加湿器はカビや雑菌の原因となり、健康に悪影響を及ぼすことがあります。
また、暖房器具を使用する際は、風が直接目に当たらないように配置を工夫しましょう。
エアコンの風向きを変えたり、風を遮るパーテーションを設置することで、目の乾燥を軽減できます。
意識的なまばたきと休息
スマートフォンやパソコン、テレビを使用する際は、意識的にまばたきを増やすことが大切です。
画面が目の高さよりも下にあると、目が自然に半開きになり、涙の蒸発を防ぎます。デスク環境を調整して、視線が少し下向きになるように配置しましょう。また、25分作業した後、5分間目を休ませる「ポモドーロ・テクニック」を活用すると、集中力が高まるだけでなく定期的に目を休めることができます。
温かい蒸しタオルで目を温めるのも効果的です。
血行が促進され、目の疲れが軽減されます。また、目の周りの筋肉もリラックスできるため、リラックス効果も期待できます。
点眼薬の適切な使用

市販のドライアイ用目薬は、手軽に目の潤いを補給できる便利なアイテムです。
ただし、注意点があります。防腐剤が入っている目薬を頻繁に使用すると、防腐剤により角膜の障害が起こることがあります。頻繁に点眼する場合には、防腐剤フリーのものを選ぶのが良いでしょう。症状が重い場合や、市販の目薬で改善しない場合は、眼科を受診して適切な治療薬を処方してもらいましょう。
また、目薬の成分によっては、角膜が荒れたり、涙の量・質が不安定になることもあります。
自己判断で長期間使用せず、症状が続く場合は必ず眼科専門医にご相談ください。
栄養と生活習慣
目の健康を保つためには、栄養バランスの良い食事も重要です。
ビタミンAやオメガ3脂肪酸を多く含む食品を積極的に摂取しましょう。ビタミンAはにんじん、かぼちゃ、ほうれん草などに、オメガ3脂肪酸はサーモン、イワシ、クルミなどに豊富に含まれています。これらの栄養素は、涙の分泌を促進し、目の表面を保護します。
十分な睡眠も大切です。
睡眠中は、目の回復が進む大切な時間です。十分な睡眠をとることで、目の疲れや乾燥を予防できます。特に、夜更かしや不規則な生活習慣はドライアイを悪化させる原因となるため、規則正しい生活を心がけましょう。
白内障治療と冬の注意点
白内障と診断されている方は、冬の環境変化に特に注意が必要です。
白内障は、一度濁ってしまった水晶体をもとに戻すことはできませんが、手術で濁った部分を取り除き、人工の眼内レンズに置き換えることで、再び明るくはっきりとした見え方を取り戻すことができます。
白内障手術のタイミング
白内障手術は、日常生活に支障が出始めたタイミングで検討することが一般的です。
「新聞がかすんで読みにくい」「夜の運転でライトがまぶしい」といった症状を感じたら、眼科専門医にご相談ください。手術は、目薬の麻酔で行う日帰り手術で、小さな切開で行うため体への負担が少なく、10分ほどで完了します。術後は、翌日から通常の生活に戻れる方が多くいらっしゃいます。
当院では、術前の検査と説明をしっかり行い、不安を解消した上で治療に進むよう心がけています。
眼内レンズの選択
白内障手術で入れる眼内レンズには、様々な種類があります。
保険適応の単焦点レンズに加え、乱視を軽減できる保険適応レンズも取り扱っています。目の状態やライフスタイルに合わせて、最適なレンズを一緒に考えていきます。大学病院での専門経験を活かし、多焦点レンズや乱視矯正レンズなど多様な眼内レンズをご提案できます。
患者さん一人ひとりのご要望をよく聞き、オーダーメイドの医療を提供することを大切にしています。
術後のケアと冬の注意点
白内障手術のあとは、数日から数週間の経過観察が大切です。
術後の目の回復を丁寧にチェックし、見え方の安定をしっかりサポートします。目薬の使用や生活上の注意点も、わかりやすく説明いたします。特に冬は乾燥しやすいため、術後のドライアイ対策も重要です。適切な点眼薬の使用と、室内環境の調整を心がけましょう。
こんな症状があれば眼科受診を

以下のような症状を感じたら、早めに眼科を受診することをおすすめします。
目がかすんで見えにくい・・・白内障やドライアイの可能性があります。特に、メガネを変えても見え方が改善しない場合は注意が必要です。
まぶしくて外出や運転が不安・・・白内障の典型的な症状の一つです。夜間の運転時にライトがまぶしく感じる場合は、早めの診断が重要です。
目の充血やかゆみが続く・・・結膜炎やアレルギー性疾患の可能性があります。自己判断で市販薬を使い続けず、眼科専門医にご相談ください。
急激な視力低下・・・網膜の血管閉塞など、緊急性の高い疾患の可能性があります。すぐに眼科を受診してください。
目の奥の痛みや違和感・・・緑内障や眼圧上昇の可能性があります。放置すると視野欠損が進行することがあるため、早期の検査が必要です。
白内障は、早めの診断と適切な時期での手術がとても大切です。「見えにくさ」を感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
冬は、乾燥や寒さ、気温の変化など、目にとって厳しい環境が続きます。
白内障そのものが冬に急激に悪化するわけではありませんが、ドライアイや目の乾燥といった冬特有の症状が重なることで、見えにくさを強く感じることがあります。また、網膜の血管閉塞や結膜炎など、冬に起こりやすい眼科疾患にも注意が必要です。
室内の湿度管理、意識的なまばたき、適切な点眼薬の使用、栄養バランスの良い食事、十分な睡眠・・・これらの日常的な対策を心がけることで、冬の目のトラブルを予防できます。
そして何より大切なのは、少しでも異常を感じたら早めに眼科を受診することです。
患者さん一人ひとりの生活が、再び明るく見えるようサポートいたします。目の健康に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
幕張久木元眼科では、「高度医療をあたたかく提供する」「自分が受けたい眼科診療」を理念に掲げ、白内障の診断から手術、術後のケアまでを一貫して行っています。土日祝日も診療しており、イオンモール幕張新都心内という便利な立地で、皆様の目の健康をサポートしています。
詳しい診療内容や白内障手術については、幕張久木元眼科の公式サイトをご覧ください。WEB予約も可能ですので、待ち時間を有効活用しながら受診いただけます。
著者情報
幕張久木元眼科 院長 久木元 延行

経歴
獨協医科大学 医学部医学科卒業
東京医科歯科大学病院 臨床研修医
東京医科歯科大学 眼科学講座 入局
東京都立広尾病院 眼科
東京医科歯科大学病院 眼科
東京都立多摩総合医療センター 眼科
東京医科歯科大学病院 眼科
– 白内障・屈折矯正外来 主任
– 糖尿病網膜症専門外来
– 医療安全管理リスクマネージャー
幕張久木元眼科開院
資格
日本眼科学会認定眼科専門医
水晶体嚢拡張リング認定医
難病指定医
ボトックス認定医(眼瞼痙攣、斜視)
光線力学療法認定医
所属学会
日本眼科学会
日本眼手術学会
日本白内障屈折矯正学会
日本網膜硝子体学会
日本糖尿病眼学会




