目がまぶしい症状は病気のサイン?5つの原因と対策を眼科医が解説
- 2025年11月19日
- 眼科
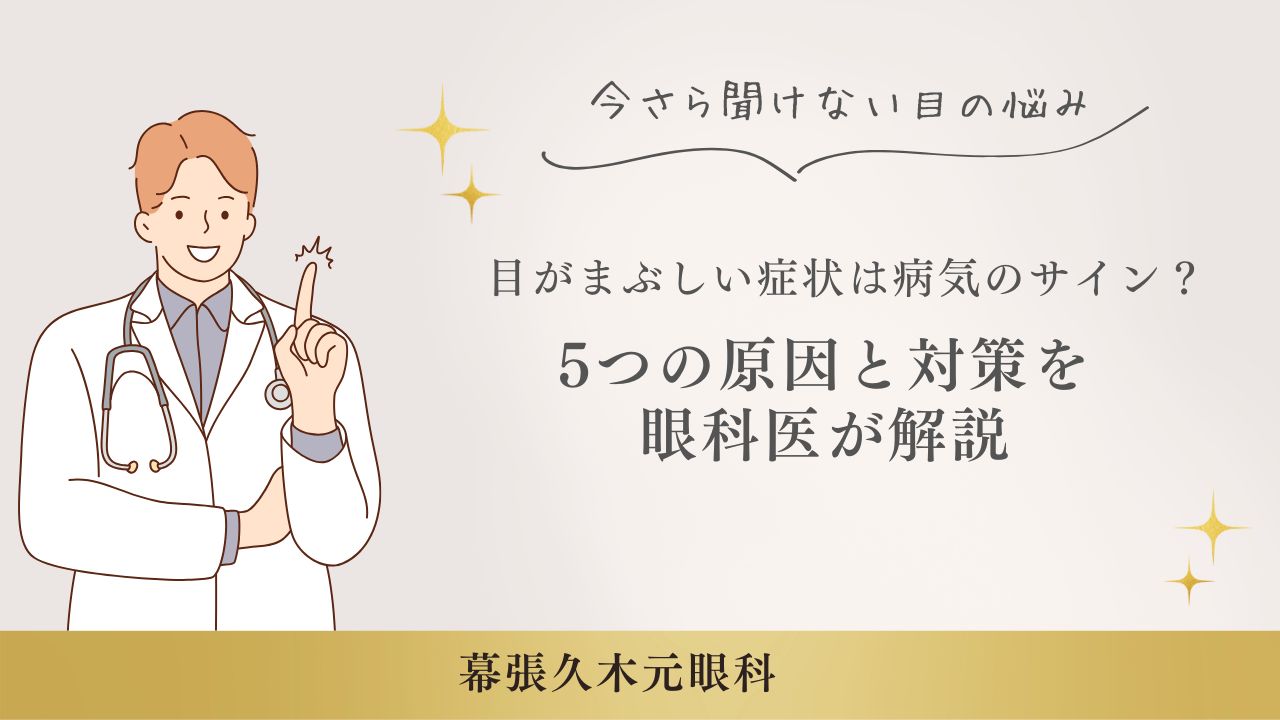
目がまぶしい症状の正体~羞明(しゅうめい)とは
普通の明るさなのに「まぶしくて目が開けられない」「室内の照明が急に眩しく感じる」という経験はありませんか?
このような症状は、医学的には「羞明(しゅうめい)」と呼ばれる状態です。羞明とは、通常の光の強さでも過剰にまぶしく感じ、時には目の痛みや涙が出るなどの症状を伴うことがあります。
私は眼科医として多くの患者さんから「最近、光がまぶしくて運転に支障が出る」「スマホの画面がまぶしくて長時間見ていられない」といった訴えを聞きます。このような症状は単なる「光に弱い体質」ではなく、目の健康状態からのSOSサインかもしれません。
羞明を引き起こす主な原因は、大きく分けて3つあります。
- 目に入る光の量がうまく調整できていない
私たちの目には、光の量を調節する「虹彩(こうさい)」という器官があります。暗いところでは瞳孔を開いて多くの光を取り込み、明るいところでは瞳孔を閉じて光の量を制限します。しかし、何らかの原因で虹彩の機能に障害が生じると、光の量を適切に調節できなくなり、まぶしさを感じるようになります。
- 目に入る光が散乱している
通常、目に入った光はきれいに屈折して網膜に届きます。しかし、角膜や水晶体に異常があると、光が乱反射して散乱し、まぶしさや不快感を引き起こします。
- 網膜や視神経のトラブル
網膜や視神経に問題があると、正常な光の量でもまぶしく感じることがあります。これは神経系の疾患が関与している可能性があります。
目がまぶしい症状から考えられる5つの病気
まぶしさを感じる原因となる代表的な病気について詳しく見ていきましょう。
日常生活に支障をきたすほどのまぶしさは、何らかの目の病気が隠れている可能性があります。早期発見・早期治療が大切ですので、気になる症状があれば我慢せず眼科を受診することをお勧めします。
- 白内障
白内障は、眼球内のレンズの役割をする水晶体が濁る病気です。加齢によるものが最も一般的で、50歳頃から徐々に進行し始めます。水晶体が濁ると、そこを通過する光が乱反射を起こし、まぶしさを感じるようになります。
特に夜間の運転中に対向車のヘッドライトがギラギラと見える、太陽の光が異常にまぶしく感じるといった症状が特徴的です。また、視界全体がかすんだり、ぼやけて見えたりすることもあります。
白内障は加齢による老化現象の一つで、誰にでも起こりうるものです。進行速度には個人差がありますが、60~70歳頃になると「眼鏡をかけても新聞がかすんで見えない」「運転時にまぶしくて怖い」といった症状が現れ、日常生活に支障をきたすようになることがあります。
残念ながら、濁ってしまった水晶体を元の透明な状態に戻す方法はありません。進行を遅らせる目薬はありますが、根本的な治療には手術が必要です。
- ドライアイ

ドライアイは、目の表面を潤す涙が不足したり、質が低下したりすることで起こる病気です。涙の量が減ると角膜の表面がでこぼこになり、光が乱反射してまぶしさを感じるようになります。
目の乾燥感やゴロゴロ感、疲れやすさなどの症状も伴うことが多いです。長時間のパソコン作業やスマホの使用、コンタクトレンズの装用、エアコンの効いた乾燥した環境などが原因となります。
どうですか?このような症状に心当たりはありませんか?
- 角膜炎
角膜炎は、目の表面を覆う透明な膜である角膜に炎症が起きた状態です。細菌やウイルスの感染、コンタクトレンズによる傷、異物の混入などが原因となります。
まぶしさの他に、目の痛み、充血、涙目、視力低下などの症状が現れます。放置すると視力に悪影響を及ぼすことがあるため、早めの治療が必要です。
意外と知られていない目のまぶしさの原因
一般的な目の病気以外にも、まぶしさを引き起こす原因があります。これらは見落とされがちですが、日常生活の中で気をつけるべき重要なポイントです。
- ぶどう膜炎
ぶどう膜炎は、眼球の中間層である「ぶどう膜」に炎症が起きる病気です。ぶどう膜は虹彩、毛様体、脈絡膜からなり、血管が豊富な組織です。
炎症が起きると、まぶしさの他に、目の痛み、充血、視力低下、飛蚊症(目の前を小さな虫や糸くずのようなものが飛んで見える症状)などが現れます。
ぶどう膜炎は感染症が原因で起こる場合と、サルコイドーシスなどの全身疾患に伴って起こる場合があります。重症のものは失明の恐れもあるため、早期発見・早期治療が重要です。
- 眼精疲労・VDT症候群
現代社会では、パソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイスを長時間使用する機会が増えています。これにより、目に過度の負担がかかり、眼精疲労やVDT(Visual Display Terminal)症候群を引き起こすことがあります。
症状としては、まぶしさの他に、目の疲れ、頭痛、肩こり、集中力の低下などが現れます。デジタルデバイスから発せられるブルーライトも目の負担を増加させる要因の一つです。
1日中デスクワークをしている方は、1時間に1回は休憩を取り、遠くを見るなどして目を休ませることが大切です。また、画面との距離を40cm以上保ち、ブルーライトカット機能付きの眼鏡を使用するのも効果的です。
瞳の色が薄い方も、まぶしさを感じやすい傾向があります。日本人は一般的に瞳の色が濃い茶色ですが、薄い茶色の方は光を通しやすいため、まぶしさを強く感じることがあります。
目がまぶしい症状への効果的な対策と治療法
まぶしさに悩まされている方に、効果的な対策と治療法をご紹介します。原因によって適切な対処法が異なりますので、自分の症状に合った方法を選びましょう。

日常生活での対策
サングラスの活用
外出時には、UVカット機能付きのサングラスを着用しましょう。特に晴れた日や雪山、海辺など光の反射が強い場所では効果的です。サングラスは目に入る光の量を減らし、紫外線からも目を守ってくれます。
室内照明の調整
室内の照明が明るすぎる場合は、少し暗めに調整するか、間接照明を取り入れましょう。特にパソコンやスマホを使用する際は、画面の明るさも適切に調整することが大切です。
ブルーライト対策
デジタルデバイスから発せられるブルーライトは目の負担となります。ブルーライトカット機能付きの眼鏡やスクリーンフィルターを使用したり、デバイス自体のブルーライト軽減機能を活用したりすることで、目への負担を軽減できます。
適切な休息
長時間のデジタルデバイス使用は避け、定期的に休憩を取りましょう。20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先を見る「20-20-20ルール」を実践するのも効果的です。
目の健康を守るためには、日々の小さな習慣が大切なんですよ。
医療機関での治療
自己対策で改善が見られない場合や、症状が重い場合は、眼科を受診しましょう。原因となる疾患に応じた適切な治療を受けることが重要です。

白内障の治療
白内障の根本的な治療は手術です。濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズを挿入します。現在の白内障手術は日帰りで行われることが多く、約10分程度で終了します。術後の見え方は格段に改善し、まぶしさも軽減されます。
当院では保険適用の乱視矯正可能な単焦点レンズも取り扱っており、「眼鏡をかけなくてもよく見える」ことにこだわった治療を提供しています。軽度の乱視でも適応があれば積極的に乱視矯正を行い、術後のQOL向上を目指しています。
ドライアイの治療
ドライアイには人工涙液や涙の蒸発を防ぐ目薬を使用します。重症の場合は涙点プラグという、涙の排出口をふさぐ治療も効果的です。また、生活習慣の改善や室内環境の湿度管理も重要です。
角膜炎・ぶどう膜炎の治療
原因に応じた抗菌薬や抗ウイルス薬、抗炎症薬などを使用します。症状が重い場合は入院治療が必要になることもあります。早期発見・早期治療が視力維持の鍵となります。
まぶしさを感じたら早めに眼科受診を
目のまぶしさは、単なる不快感ではなく、重要な目の健康シグナルです。特に以下のような場合は、早めに眼科を受診することをお勧めします。
- 急にまぶしさを感じるようになった
- まぶしさと同時に目の痛みや充血がある
- 視力低下を伴っている
- 日常生活や運転に支障をきたしている
- 自己対策を試しても改善しない
眼科での検査は、視力検査、細隙灯顕微鏡検査(目の前面を詳しく観察する検査)、眼圧検査などが基本となります。必要に応じて散瞳検査(瞳孔を広げて眼底を観察する検査)も行います。散瞳検査後は3~5時間程度、自動車やバイクの運転ができませんので、ご注意ください。
目は外界の情報の約8割を取り入れる重要な感覚器官です。その健康を守ることは、質の高い生活を送るために欠かせません。
「最近、光がまぶしくて気になる」と感じたら、それは目からのSOSサインかもしれません。我慢せずに専門医に相談することで、早期発見・早期治療につながります。
あなたの目の健康は、私たち眼科医がしっかりとサポートします。
まとめ
目のまぶしさは、白内障、ドライアイ、角膜炎、ぶどう膜炎、眼精疲労など様々な原因で起こります。特に加齢による白内障は50歳頃から徐々に進行し始め、60~70歳頃には日常生活に支障をきたすことがあります。
対策としては、サングラスの着用、室内照明の調整、ブルーライト対策、適切な休息などがあります。症状が重い場合や自己対策で改善しない場合は、眼科を受診して適切な治療を受けることが大切です。
目のまぶしさを放置せず、早めに対処することで、快適な視生活を取り戻しましょう。
著者情報
幕張久木元眼科 院長 久木元 延行

経歴
獨協医科大学 医学部医学科卒業
東京医科歯科大学病院 臨床研修医
東京医科歯科大学 眼科学講座 入局
東京都立広尾病院 眼科
東京医科歯科大学病院 眼科
東京都立多摩総合医療センター 眼科
東京医科歯科大学病院 眼科
– 白内障・屈折矯正外来 主任
– 糖尿病網膜症専門外来
– 医療安全管理リスクマネージャー
幕張久木元眼科開院
資格
日本眼科学会認定眼科専門医
水晶体嚢拡張リング認定医
難病指定医
ボトックス認定医(眼瞼痙攣、斜視)
光線力学療法認定医
所属学会
日本眼科学会
日本眼手術学会
日本白内障屈折矯正学会
日本網膜硝子体学会
日本糖尿病眼学会




